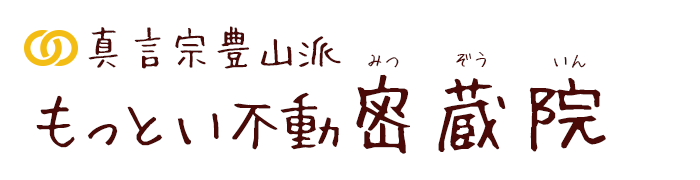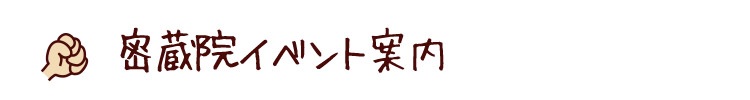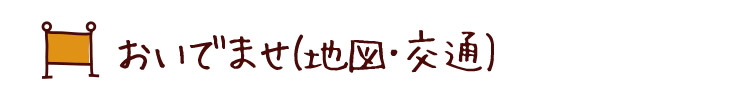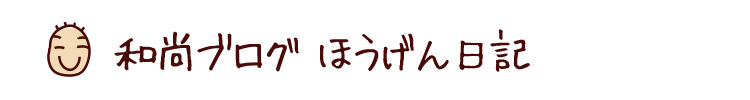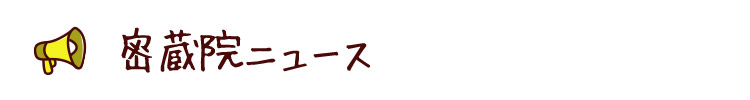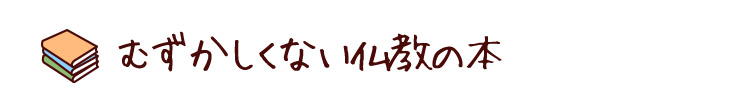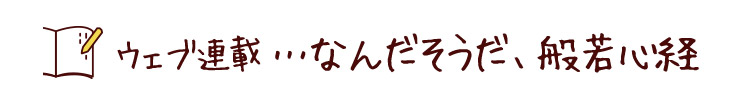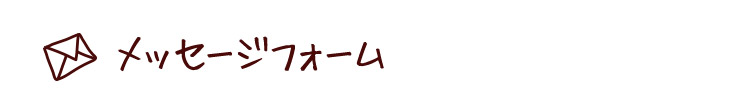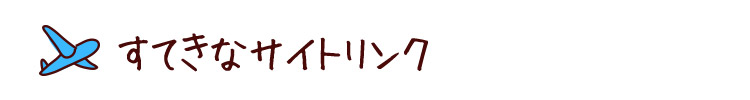森鴎外は短編『寒山拾得』(著作権の関係で、ネットの青空文庫で無料で読めます)の中で、作品の途中でまるで「注意書き」のような形で下記の一文を挟んでいる。私がこ一文に感激、感動したのは20代だった。おかげで、自分が歩いている道(仏道)がどんなものか、そして注意点がわかった。茶道、華道、合気道などをやっている方、やろうとしている方は知っておいたほうがいいと思う。
「全体世の中の人の、道とか宗教とかいうものに対する態度に三通りある。自分の職業に気を取られて、ただ営々役々と年月を送っている人は、道というものを顧みない。これは読書人でも同じことである。もちろん書を読んで深く考えたら、道に到達せずにはいられまい。しかしそうまで考えないでも、日々の務めだけは弁じて行かれよう。これは全く無頓着な人である。
つぎに着意して道を求める人がある。専念に道を求めて、万事をなげうつこともあれば、日々の務めは怠らずに、たえず道に志していることもある。儒学に入っても、道教に入っても、仏法に入っても基督教に入っても同じことである。こういう人が深くはいり込むと日々の務めがすなわち道そのものになってしまう。つづめて言えばこれは皆道を求める人である。
この無頓着な人と、道を求める人との中間に、道というものの存在を客観的に認めていて、それに対して全く無頓着だというわけでもなく、さればと言ってみずから進んで道を求めるでもなく、自分をば道に疎遠な人だと諦念(あきら)め、別に道に親密な人がいるように思って、それを尊敬する人がある。尊敬はどの種類の人にもあるが、単に同じ対象を尊敬する場合を顧慮して言ってみると、道を求める人なら遅れているものが進んでいるものを尊敬することになり、ここに言う中間人物なら、自分のわからぬもの、会得することの出来ぬものを尊敬することになる。そこに盲目の尊敬が生ずる。盲目の尊敬では、たまたまそれをさし向ける対象が正鵠を得ていても、なんにもならぬのである。」