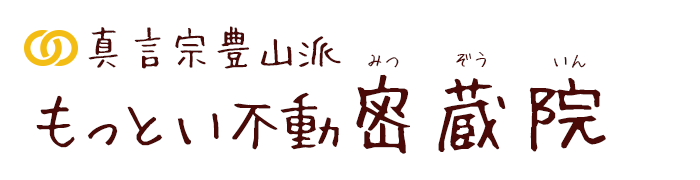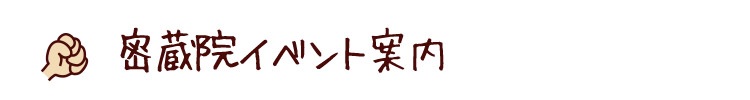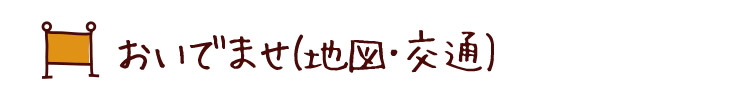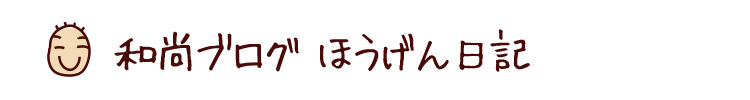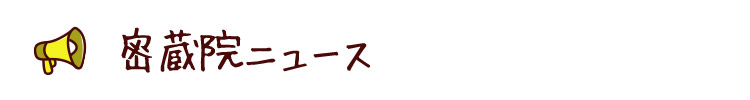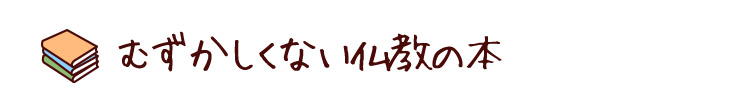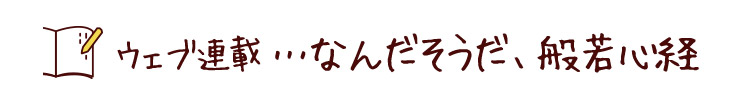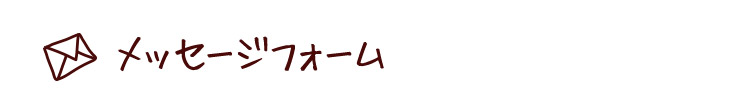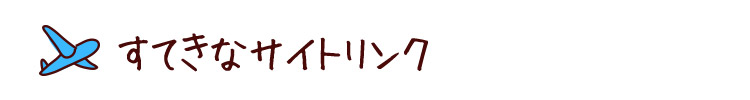江戸の六割を焼きつくした(七割とも)、この明暦の大火は、通称「ふりそで火事」と言われました。これ以降、江戸の町には各所に防火のための広小路が整備されるなど、江戸の町の大整備事業が行われたのでございます。
この火事で焼けた本願寺は、同じ場所に造営されることは許されず、信徒の力で海を埋め立てて造れというお触れがでました。全国の信徒が浄財をつのり、また人力を出して海に地面を築いたことから、この地を「築地」と言うのはご存じの通りでございます。
また、吉祥寺の門前に住んでいた人々は、移住を余儀なくされまして、新しい土地をもらいましたが、信仰篤き人々ゆえ、自分たちの町を「吉祥寺」と名づけ、今や若者が一番住みたい町のトップに君臨しているもの耳新しいことでございますまい。
一方、江戸は火事が多いというので、紀伊国屋の番頭の長五郎は関東一円の山の材木、数年前から手付けの金を払ってある。そればかりでなく、わらじ、鋤、桑などを買い占めておりました。江戸市中で家の普請、大名屋敷の造営にかかりますと、すべて紀伊国屋から物を買わなければなりません。 こうして紀伊国屋は、紀州からでてきて一代で百万両の身代に相成りました。文左衛門はその後、享保十九年六十六歳を一期(いちご)として四月二十四日に死去。辞世の句に「西に行く 道も明るし 桜時」。
こうして紀伊国屋は、紀州からでてきて一代で百万両の身代に相成りました。文左衛門はその後、享保十九年六十六歳を一期(いちご)として四月二十四日に死去。辞世の句に「西に行く 道も明るし 桜時」。
「振り袖火事」にまつわるお話は、外にも数々ありますが、ここいらで、『定本講談名作全集第二巻』(講談社)-紀伊国屋文左衛門-の中のスピンオフ作品「振り袖火事」の読み終わりでございます。何となく聞いたことがある江戸の「振り袖火事」の顛末、お読みいただきとまして、ありがとうございました。