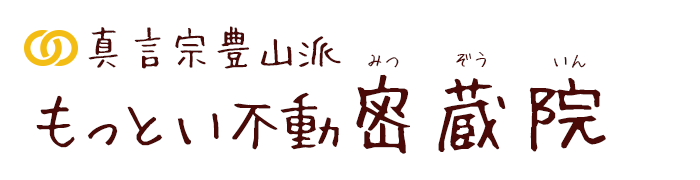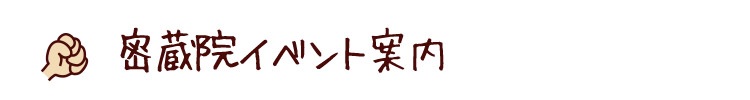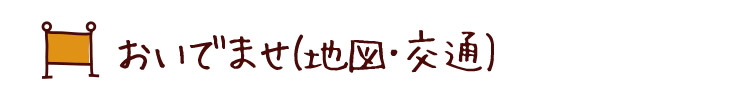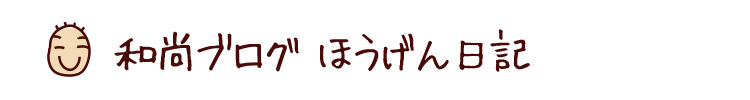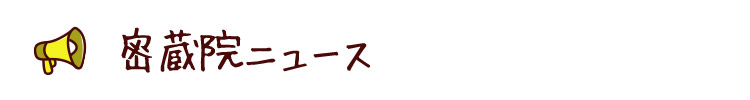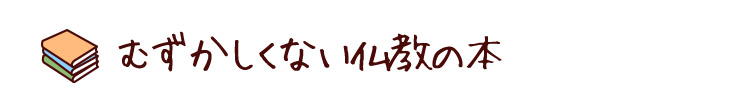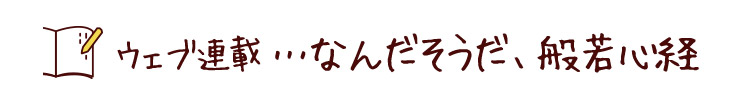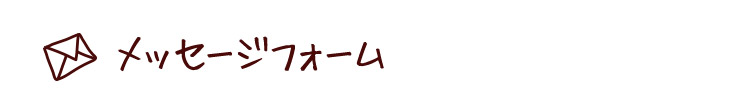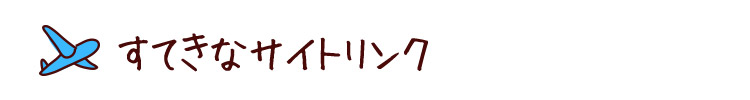吹き来たった風にあおられて、火のついた振袖が宙に舞いました。それを見た野次連。「おお、見ろ見ろ。火のついた振袖が人間が着たようになって、風の間に間にあちらこちらへ飛んでいやがる」「なるほどこんなのは芝居じゃ見られねぇ。おっといけねぇ。お寺の庇に火がついたぞ」
もともと振袖のことですから、そんなに長くは燃えていない。火は消えて振袖は灰になりました。「ああ、良かった。あの火が屋根裏についたら大事になる」「これで家に帰っていいみやげ話ができたな」
と呑気なことを言っていると、本堂の屋根の破風(はふ)の間からボーッと黒い煙がでた。「やぁ、大変だ。消えたんじゃねぇ。火がついた。本物だ。大変だ、大変だ」
あわてた住職が、「誰か早く鐘をついて火消しを呼べ」。役僧もあわててはしごを登って半鐘をつこうとすると、煙の中に入ってしまったか、真っ暗で半鐘が見えない。「まったく、どうなっているのだ」と言っていると、下から「半鐘の中に首をつっこんで何をしてるんだ。バカ坊主。あわてるにも程がある」
そうこうしている間に、本妙寺の本堂の屋根裏は火の海。この火が消えないうちに、湯島六丁目の円満寺へ飛び火し、ついでお茶の水にある吉祥寺という大寺へ火がついた。この火が、駿河台鈴木町の旗本屋敷に移り、その火は高台から内神田へ。とても消火は間に合いません。一夜開けて翌日十九日には、牛込鷹匠町から再び火の手があがり、江戸城本丸へ火が移り、芝まで及びます。さらに、くすぶった火が翌二十日には、麹町から出火。まさに燎原の火のごとし。
こうして、通り魔によって三人の娘につけられた怪異な火は振り袖の陰気な火として受け継がれ、やがて三日間の大火事となり、江戸八百八町を焼き立てたのでございます。火事や他の原因で亡くなったその数、十万八千人と言われます。その亡骸は本所牛島の空き地へ穴を掘りましてここに埋め、公儀の手でお寺を建てたのが八州山無縁寺、今日の両国回向院でございます。
今日はここまで、いよいよ明日はまとめでございます。