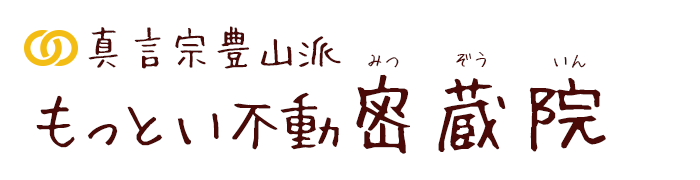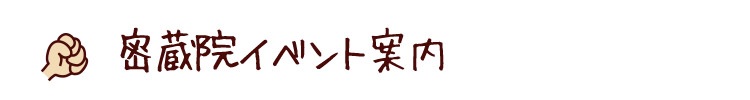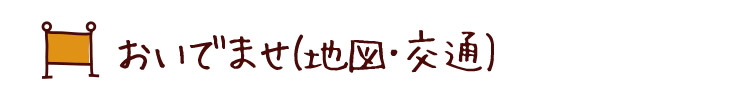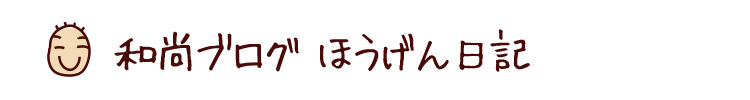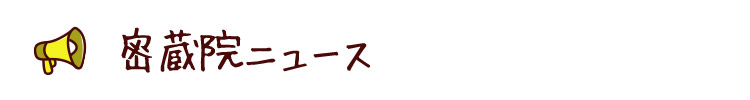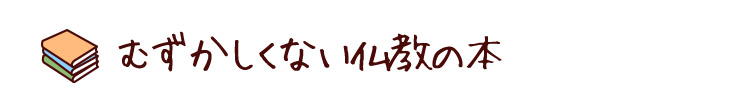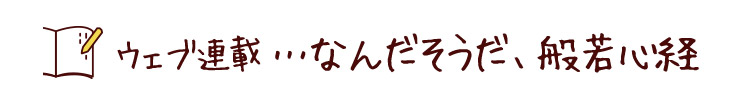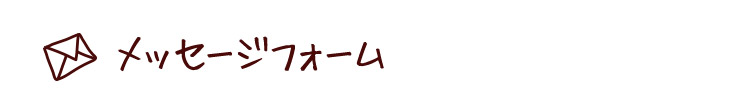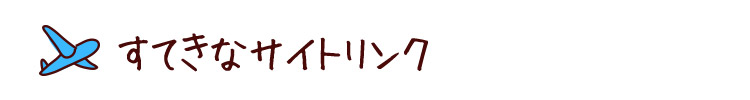今日のご詠歌の休憩時間。桜の話題が真っ盛りなので、恒例の「姥桜(うばざくら)」の意味をプリントして渡した。姥桜(うばざくら)は葉にさきだって花を開く桜の総称だが、【広辞苑】では、娘盛りが過ぎてもなお美しさが残っている年増。女盛りの年増。【明鏡国語辞典】では、〔俗〕年齢をかさねても、なお色気のある女性。※ 花(色気)はあっても葉(歯)がない意からという。【新明解国語辞典】は、かなりの年増(トシマ)であるが、なまめかしさを漂わせている女性。【標準国語辞典】では、若いさかりを過ぎても、まだなまめかしさのある女性。--である。すると講員さんから「年増っていくつのことですかね」というもっともな疑問。で、大辞林で調べたら、大変なことになった。曰く「年増(としま):江戸時代では20歳前後、昭和の時代では30歳~40歳の女性のこと」とある。「じゃ、私たちではないんですね。では、私たちは何者なのでしょう」と言う。喜ばせるつもりの姥桜の解説が、悲惨な結果になってしまった。ぐはは。ガンバレ、姥姥桜!あはは。
和尚ブログ ほうげん日記
2018年03月26日